『聲の形』を観終えたあと、感動の涙を流す方がいる一方で、こんな声もよく聞かれます。
「登場人物、全員嫌いだった」「誰にも好感が持てなかった」「救いがなさすぎる」。
この“重さ”や“息苦しさ”に戸惑い、心の中にモヤモヤが残ったまま、エンディングを迎えた方も多いのではないでしょうか。
石田将也、西宮硝子、川井みき、島田一旗――彼らは皆、強い個性と欠点を抱え、「性格が悪い」とすら評されることもあります。
誰か一人に感情移入するのが難しい、そんな不器用で自己中心的で、未熟な人たち。でも、だからこそ、この作品は一部で強く批判されながらも、深く支持されているのです✨
実は、作者の大今良時さん自身も「キャラクターは全員嫌いだった」と語っています。
でもそれは、ただの否定ではありません。“嫌い”から描きはじめるという、表現者としての大きな覚悟がそこにはあるのです。
この記事では、『聲の形』の登場人物たちがなぜ「好かれないように」描かれたのか、その不快感の中に隠された意図とリアリティを、作者のインタビューや作品の構造、SNSの声などを交えながら紐解いていきます。
「嫌悪の先にある赦しの余白」とは何か――そこに、この作品の核心があるのかもしれません💫
「登場人物に好感が持てない」声が多い理由

※イメージです
『聲の形』は、多くの賞賛を集めた一方で、「感動できなかった」「キャラクターが全員不快だった」という声も多く見られます。
石田、西宮、川井、島田――それぞれが過ちや弱さを抱えており、そのリアルさゆえに、観ていてしんどくなる方もいるかもしれません😢
特に、いじめの加害者だった石田の視点で物語が展開されることや、西宮の自殺未遂、川井の自己保身、島田の無反省など、観ていて“救いのない”展開が続くことで、「感動モノ」にはありがちなカタルシスや成長譚がありません。
でもそれは、作者・大今良時さんがあえて「わかりやすい魅力」を排除したからなのです。
そこには、リアルな人間を誠実に描こうという強い意志がありました。
作者・大今良時のインタビュー・背景

※イメージです
作者の大今さんは、インタビューで「正直、登場人物みんな嫌いでした。
でも、描くことでちょっとずつ好きになっていきました」と語っています。
この言葉からわかるのは、最初から「愛すべき存在」としてキャラを描いていたわけではなかったということ。
むしろ、人間の嫌な部分――目を背けたくなるような弱さや不完全さから目を逸らさず、それを丁寧に描き出すことにこそ、表現者としての誠実さを込めていたのです。
また、大今さんは「耳の聞こえない人のことを何も知らなかった」とも話しており、丁寧に取材を重ねて当事者の声を聴きながら制作を進めたそうです。
このような誠実な姿勢が、「誰にでも好かれる」作品とは正反対の、鋭くて深いキャラクター表現を生んだのです🍀
キャラの“性格の悪さ”は意図的なものか?

※イメージです
『聲の形』に登場するキャラクターたちが見せる“性格の悪さ”――これは偶然ではなく、明確な意図に基づいています。
石田の自己嫌悪、西宮の自己否定、川井の偽善、島田の無神経。どれもが、現実にいそうな「理想的ではない人間像」なんです。
フィクションではどうしても「いい人」「成長する主人公」を求めてしまいがち。
でもこの作品は、「人間って、そんなに簡単に変われないよね」という現実を突きつけてきます。
つまり、“性格の悪さ”はキャラを嫌わせるためではなく、「現実の人間の複雑さを正面から描くため」に必要だったのです。
そう考えると、大今さんの描写はとても誠実で、深い意味を持っていると感じます🌱
現実の複雑さを描く=嫌われる構造
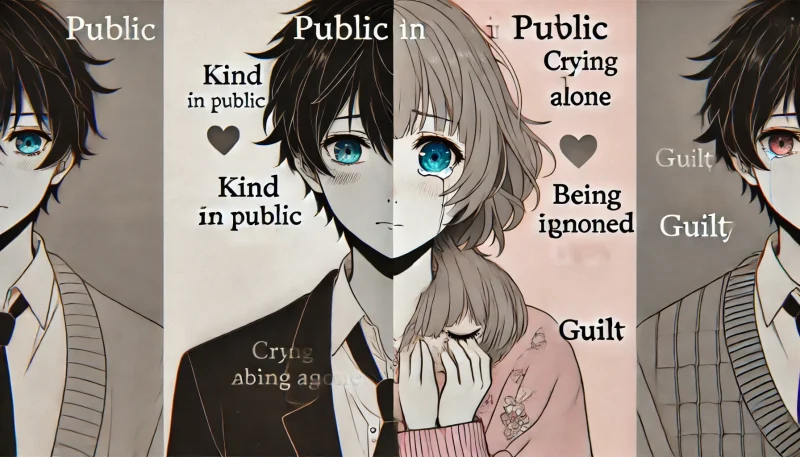
※イメージです
多くのフィクションでは、被害者と加害者、善と悪がはっきり分かれていますよね。でも『聲の形』は、その境界線を曖昧にしています。
だから観ている側も、「誰を応援すればいいのか分からない」「みんな中途半端に悪くてストレスを感じる」といった戸惑いが生まれるんです。
それでも大今さんは、“嫌われること”を恐れずに、この複雑さと矛盾を描く道を選びました。
だからこそ、この物語は「スッキリ終わる」ものではなかったのです。
「救いのなさ」ではなく「赦しの余白」

※イメージです
『聲の形』には、明確な救済や和解のシーンはありません。
謝ってスッキリ、成長して感動――そんな展開は一切なく、すべてが“途中のまま”終わっていきます。
だからこそ、「救いがない」「重いだけだった」と感じる方もいると思います。
でも、実はその“余白”こそが、この作品の本質。
石田や西宮がすべてを乗り越えたわけではありません。川井や島田も心から反省したとは言えません。
それでも少しずつ、少しずつ、他人と向き合おうとする小さな歩みが、物語に“赦し”の種を蒔いていきます。
この物語は、「赦した物語」ではなく、「赦していく過程を描いた物語」なのです🌸
SNS・レビューでの賛否紹介

※イメージです
SNSやレビューを覗いてみると、『聲の形』はたくさんの感動を呼ぶ一方で、強い批判も受けています。
🟢 賛の声
・「人間の弱さをここまでリアルに描いた作品はない」
・「キャラが嫌いだったけど、最後にはその不完全さに涙した」
・「赦すことの難しさを考えるきっかけになった」
🔴 否の声
・「誰にも共感できない」「いじめを正当化しているように見える」
・「不快なキャラばかりで観ていられなかった」
・「結局、何が言いたかったのか分からない」
この賛否こそが、『聲の形』が“誰の味方にもならない物語”である証拠です。
誰かを美化することなく、悪者にすることなく、私たちに問いかけ続けてくれる作品なんです。
表現者としての覚悟と反応
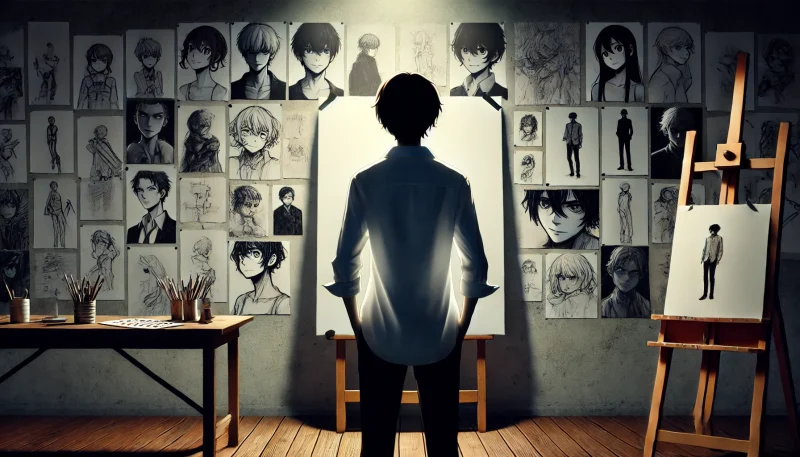
※イメージです
大今さんが『聲の形』で描いたのは、「感動モノ」ではなく、人と人との“届かなさ”や“不器用さ”、それでも向き合おうとする心です。
それは、読んでいて苦しくなるような話かもしれません。でもだからこそ、本当に意味のある物語だと思います。
好かれないキャラクター、赦しきれない結末、それを描ききったのは、表現者としての“媚びない覚悟”の表れ。
問いを投げかけることに徹したその姿勢が、多くの人の心に長く残っているのだと思います✨
まとめ:嫌悪から始まる共感の可能性

※イメージです
『聲の形』に登場するキャラクターたちは、決して理想的ではありません。
むしろ、「なんでこんな人ばかりなの?」と思ってしまうかもしれません。
でも、そうした「嫌悪」こそが、私たちの心に強く残り、自分の中の感情と向き合わせてくれるきっかけになるんです。
大今さんは、そんな“不完全な人たち”を裁くことも、美化することもなく、ただ誠実に描き続けました。
だからこそ、この物語は読んだ人それぞれの「自分自身と向き合う物語」になるのです🌈
嫌いから始まる共感もある――
それが『聲の形』という作品が、今も語り継がれる理由のひとつなのかもしれません。







