『聲の形』がなぜ“いじめの美化”と批判されるのか、その理由と背景を丁寧に検証しながら、他のいじめを扱った作品との比較も交え、作品が本当に私たちに問いかけているものは何か――その本質に迫っていきます。
いじめを「描くこと」自体が持つ社会的意義とリスク、その両方を見つめながら、今一度この物語を読み解いてみましょう。
問題提起:なぜ“美化”と批判されるのか
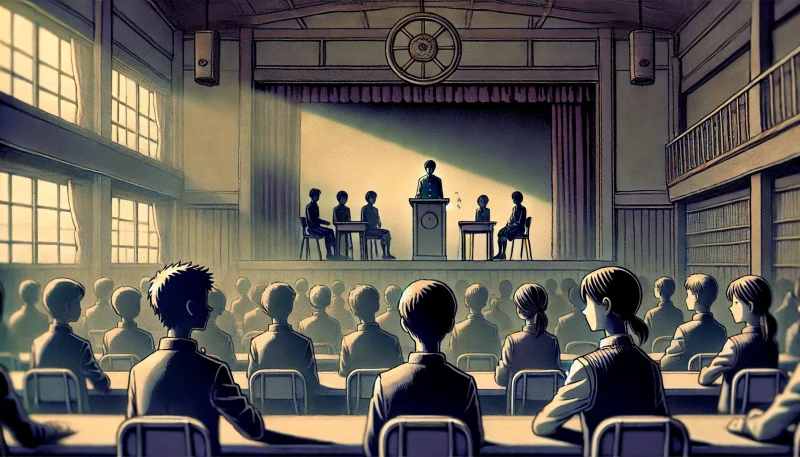
※イメージです
2016年に公開された映画『聲の形』は、感動作として大きな注目を集めました✨
けれど同時に、「いじめを美化しているのでは?」という疑問や批判も根強く存在しています。
とくにSNSやレビューサイトでは、「加害者側の感情ばかりが描かれていて、被害者へのフォローが足りない」という声も少なくありません。
こうした評価が割れる理由には、作品が持つ複雑さと誠実さがあるんです。
『聲の形』はただの“感動系”アニメではなく、いじめという重く深刻なテーマに正面から向き合った挑戦作でもあるからこそ、見る人の立場や経験によって受け止め方が大きく変わってしまうのです。
作中のいじめ描写のリアルさと痛み

※イメージです
物語の序盤では、聴覚障害のある少女・西宮硝子が、クラスメイトたちから繰り返しいじめを受けるシーンが描かれます。
中心にいたのは、主人公の石田将也。
補聴器を壊す、からかう、無視する…。
これらの行為は、決して“創作の世界だけの出来事”ではありません。
むしろリアルで、観る側の胸にズシンと響くような痛みがあります😣
さらに注目したいのが、周囲の大人の無関心や、クラスの空気といった「いじめを生む構造」が丁寧に描かれていること。
『聲の形』は、“誰かが悪い”という単純な描き方ではなく、「こうして、みんなが無意識のうちに加害者になっていく」現実に向き合っているんです。
被害者と加害者の心情の両方を描く構造

※イメージです
本作の最大の特徴は、加害者である石田将也の視点で物語が展開するという点。
ここがまさに、「美化だ」と感じる人と、「贖罪の物語だ」と受け取る人で評価が分かれるところなんですね。
石田は、いじめが発覚したことで一転、周囲から孤立し、友達を失い、自分を深く責めながら生きるようになります。
彼の苦しみや変化、そして再び他者とつながろうとする姿が、作品全体の柱となっています。
一方、被害者である西宮硝子の心情も描かれていますが、どうしても“石田の内面”に物語の重心が置かれている印象は否めません。
だからこそ、「被害者の苦しみより、加害者の再生を優先している」と受け取る人がいても不思議ではないのです💭
川井・島田・石田のそれぞれの“逃げ”

※イメージです
作中には、石田だけでなく、いじめに関わった他のキャラクター――川井みきや島田一旗も登場します。
川井は、「私はいじめなんてしてない」と主張しつつも、実は内心で責任逃れをしていたり、被害者に寄り添う“ふり”をする場面もあります😓
島田はというと、最後まで自分の非を認めず、むしろ石田を遠ざけるような姿勢を見せ続けます。
でも、ここが『聲の形』の面白いところ。
全員が必ずしも“改心”するわけじゃないんです。
みんなが都合よく反省して、泣いて謝ってハッピーエンド――そんな単純な物語ではなく、「人は簡単には変われない」というリアルな姿が、ちゃんと描かれているんです💡
視聴者の捉え方の違い(世代・背景)

※イメージです
この作品がこれほどまでに評価が割れる理由のひとつが、観る人の背景や経験によって、感じ方がまるで変わるという点です。
いじめの被害経験がある人にとっては、加害者が主人公であることに強い違和感を覚えるかもしれません。
「自分はあんなふうに赦せなかった」「もっと描いてほしかったことがある」――そう思うのも当然です。
逆に、自分も誰かを傷つけたことがある人にとっては、石田の苦しみが他人事ではなく、むしろ共感の対象になることもあります。
さらに、今の若い世代では「謝れば終わりじゃない」「説明責任が大事」という意識が強まっており、昔よりも“贖罪”というテーマが難しくなっている背景もあるんです。
つまり、『聲の形』は人によって見え方がまったく違う。
そこにこの作品の難しさと、深さがあるんです🌊
作者のメッセージは「赦し」か「責任回避」か
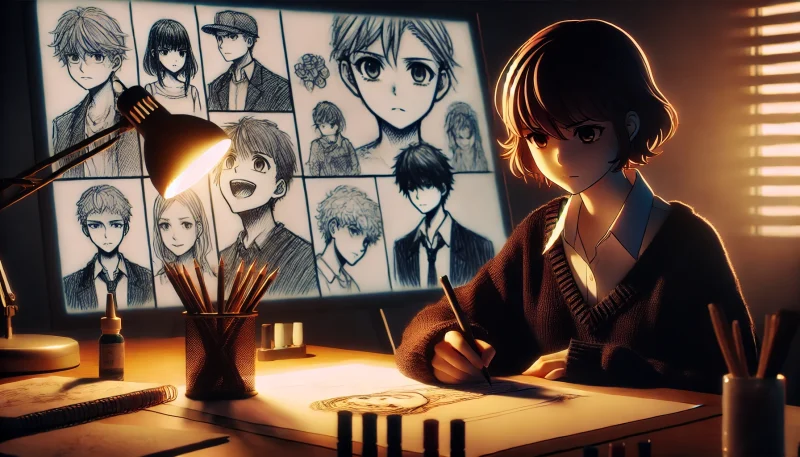
※イメージです
原作漫画の作者・大今良時さんは、この物語に「正解」を用意していません。
石田は全てを赦されるわけでもなく、西宮もすべてを許したわけではない。
中途半端で、ぎこちなくて、不器用なまま――でも、それでも前に進もうとするんです。
これは「責任逃れ」にも見えるし、「赦しへの一歩」とも取れます。
けれど、おそらく大今さんが伝えたかったのは、「向き合おうとすることの意味」ではないでしょうか。
謝ること。
許すこと。
それはどちらも簡単じゃないし、正解なんて存在しません。
だからこそ、『聲の形』は私たちに「あなたなら、どうする?」という問いを投げかけてくるんです🌱
他の作品との比較(いじめテーマ)

※イメージです
いじめをテーマにした作品は他にもたくさんあります。
たとえば、『ライフ』(すえのぶけいこ)や『十三歳のハローワーク』などは、被害者の視点に立ち、社会と闘う姿を描く作品です。
それに対して『聲の形』は、加害者側の内面に焦点を当てた、珍しい構造になっています。
これはある意味、“いじめを描く上での新しいアプローチ”だったとも言えます。
もちろん、この構成にはリスクもありますが、その分、作品としての挑戦や誠実さが感じられるのも事実です📘
まとめ:描くことで問うた社会への問い
『聲の形』はいじめを美化しているのか?
その答えは、きっと一つではありません。
けれど、この作品が「いじめを描くこと」そのものによって、私たちに静かに問いかけていることは確かです。
誰かを傷つけたことのある人。
誰かに傷つけられたことのある人。
そして、今もどこかで悩みながら生きているすべての人へ。
この作品は、“許す”とか“許される”以前に、「向き合おうとすること」の意味を伝えてくれます。
そしてその向き合い方は、不完全であってもいい。不器用でも、迷ってもいいんです。
『聲の形』は、美化ではなく、“語られない声”に耳をすますための物語だったのかもしれません🕊️💫








